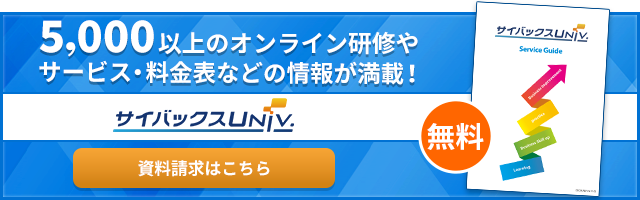最終更新日:2022年06月02日
ハラスメント問題について
多種多様な“◯◯ハラ”という単語が席巻している現代社会。このハラスメントの細分化という現象自体が、グローバルに見ると日本の特異性を示しています。
ハラスメントを包括的にとらえる定義が存在しないため、被害者自身が、自分自身が受けているのが何ハラか?を発見しないと主張し難いという現象を生み出しています。これでは、どちらが被害者で加害者なのか…という感覚にも陥りますし、申告せずに泣き寝入り…というケースも、これまでは多くあるのではないでしょうか?
「赤信号 みんなで渡れば怖くない」というギャグもあったくらいですから、自分自身はオカシイと思っていても、周囲が認めてくれるような空気感でないと申告し難いのも現状です。でも、これが、いつまでも続くのでしょうか?
注目されているハラスメント問題
日本に「ハラスメント」という単語が表舞台登場したのが、1989年に被害者である女性が裁判を起こした、「福岡セクシュアルハラスメント事件」です。1992年に女性の全面勝訴で幕を閉じたのですが、この1件を契機に、それまでは職場のいじめと捉えられていた上司の非常識な言動が「人格権の侵害」であると明確に示した点が画期的であったのです。
以降、セクハラに関しては男女雇用機会均等法において、2006年に配慮義務から措置義務へと強化され、2016年にはマタハラに関する項目も付加されています。
加えて、2017年以降、米国における「#Me Too」に端を発したハラスメントを糾弾するムーブメントが各国に波及し、日本でも政府機関、企業、大学スポーツなど、様々な組織でハラスメント事案が明るみに出ています。
もはや「バレなければOK」という感覚では対処できない時代…という認識が、組織のリーダーには必須になっていると言えます。
ハラスメントの世代間ギャップ、認識の相違
また、組織のリーダーが自覚を持って、自分自身のことだけを律すれば良いのではありません。
厚生労働省の「平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、パワーハラスメントを受けた経験のある人が32.5%存在するのに対し、「パワハラをしたと感じたり、パワハラをしたと指摘されたことがある」との回答は11.7%に留まります。
ここに年代による認識のギャップが存在します。「若い世代の我慢が足りない」「言った者勝ち」等と感じる方がいらっしゃるでしょう。また、「良かれと思って…」かけた言葉やとった行動が裏目に出ているケースもあります。
ハラスメントの基準を組織で持つ必要がある
年代によって認識が違うという時点で、年代を超える何らかの基準を組織として持たない限り、組織として防止措置義務が履行できない状態になります。この状態を放置していては、来春にも施行が予定されている「パワハラ防止法」に抵触する可能性も出てきます。
特に職業を指導する場面でパワハラとの線引きが難しいとの声もよく伺いますが、本来、実践すべきは「職業」が成果に繋がるように「指導」することであって、それほど「叱咤」がメインとなることはあり得ないのです。
世代を超えて理解し合えるガイドラインを明確化し、お互いが仕事の成果を享受できるような組織づくりに邁進すること、その模範にリーダーがならないといけないこと…この3点を実践できる状態を創出することができれば、今回の法改正を契機に業績向上へと繋がる組織行動がとれるようになるのです。
コラムの内容を学べる公開研修情報
- 『ハラスメント防止研修 ~組織としての対策』
【サイバックスUniv.事務局からご案内】
- 【無料!お役立ち資料】企業が行うべきハラスメント対策とは?
ハラスメントが企業や人に与える影響や、予防策について解説いたします。
【お役立ち資料の内容】
1.ハラスメントに対する認識
2.急増しているハラスメントの種類
3.ハラスメントが与える影響
4.ハラスメント撲滅の具体的な取り組み
5.当社サービス活用事例