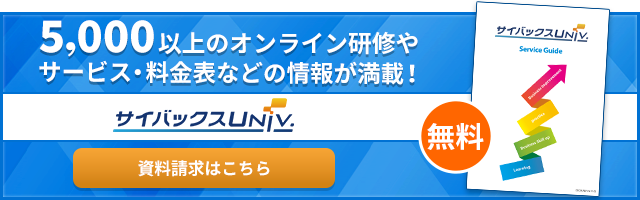1.人的資本とは?
人的資本とは、経済活動の基となる生産3要素の中のひとつ「ヒト」が持つ能力を資本としてとらえた考え方で、従業員個人が身につけている技能・技術・資格・スキル・能力等のことを指します。
一般的に「経営資源」と表現される要素の中にも「ヒト」がありますが(これを「人的資源」と呼びます)、資源は消費の対象とされ、資本は、他の「財務資本」「知的資本」「社会・関係資本」などと並んで「投資」の対象と考えられています。
2.人的資本開示という考え方と対応事例
前述の「投資対象」としての人的資本がフォーカスされるようになったのは、リーマンショックがキッカケと言えるでしょう。
投資家側から企業社会を見たときに、財務情報だけで企業価値を評価することはリスクであるという認識に至ったのです。新型コロナウィルス感染拡大の影響も大きく、従来のビジネスモデルからの変革を迫られる業界が多く存在することから、今後どう時代に適応していくのかを測る指標として注目されているのです。
加えて、「ESG投資」というトレンドも関係しています。
ESG投資とは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のことで、新しい投資評価として注目を集めています。
その一環として、「ISO30414」という新たな指標も登場しています。ISO30414とは、2018年12月に国際標準化機構(ISO)が発表した人的資本に関する情報開示のガイドラインのことです。
労働力の持続可能性をサポートするため、組織の維持・発展に対する人的資本の貢献を考察し、透明性を高めることを目的として発表されました。ガイドラインで示されている指標は下記の通りです。
| 人的資本エリア | 概要 |
|---|---|
| 1.コンプライアンスと倫理 | ビジネス規範に対するコンプライアンスの指標 |
| 2.コスト | 採用・雇用・離職等労働力のコストに関する測定指標 |
| 3.ダイバーシティ | 労働力とリーダーシップチームの特徴を示す指標 |
| 4.リーダーシップ | 従業員の管理職への信頼等の指標 |
| 5.組織文化 | エンゲージメント等従業員意識と従業員定着率の測定指標 |
| 6.健康,安全 | 労災等に関連する指標 |
| 7.生産性 | 人的資本の生産性と組織パフォーマンスに対する貢献をとらえる指標 |
| 8.採用・異動・離職 | 人事プロセスを通じ適切な人的資本を提供する企業の能力を示す指標 |
| 9.スキルと能力 | 個々の人的資本の質と内容を示す指標 |
| 10.後継者計画 | 対象ポジションに対しどの程度承継候補者が育成されているかを示す指標 |
| 11.労働力 | 従業員数等の指標 |
欧米では、人的資本開示の義務化への流れが強まっています。日本でも、2023年3月期決算より「人的資本の情報開示」が上場企業などを対象に義務化されることになっています。
アメリカでは、機関投資家からの人的情報の開示要求が強く、2020年には米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に対して人的資本の情報開示を義務づけると発表、同年11月から義務化されています。欧州でも、ドイツ銀行の傘下であるアセットマネジメント会社DWS社が、2021年に世界で初めてISO 30414の取得企業として認定された事例などがあります。
日本でも、ダイバーシティ・インクルージョンに対しての人事戦略が求められるという日本特有の事情に加え、SDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)にある「働きがいも経済成長も」への対応とも相まって、動きが加速してきています。
2021年6月に東証のコーポレートガバナンスコード改定があり、経営戦略に沿った取締役会と各取締役のそれぞれに必要なスキルの対応関係を公表すること、中核人材における多様性(ダイバーシティ)を確保することが盛り込まれています。経済産業省も、2020年に人的資本の情報開示や「高め方」、その重要性などが記されている「人材版伊藤レポート」を発表しました。
更に、2022年5月にはアップグレード版とも言える「人材版伊藤レポート2.0」をリリースしています。このレポートは、実行・実践に移すべき取り組みや、そのポイントについて「3つの視点」と「5つの共通要素」を提示しています。
<3つの視点>
・経営戦略と人材戦略を連動させるための取り組み
・「As is-To beギャップ」の定量把握のための取り組み
・企業文化への定着のための取り組み
<5つの共通要素>
・動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用
・知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取り組み
・リスキリング 学び直しのための取り組み
・社員エンゲージメントを高めるための取り組み
・時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取り組み
人的資本経営の事例については、以下で公開されています。
経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~人材版伊藤レポート2.0~ 実践事例集事例集」(2022年5月)
3.人的資本情報開示の義務化への準備と対策
この人的資本開示というトレンドは、かつての「株主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」への転換を意味しています。
「ヒトという無形資産への投資とその情報開示を前向きに行っている企業に資金が集まる仕組みをつくり、企業競争力の底上げにつなげ、その果実をステークホルダーに還元する」という仕組みづくりと捉えることができるからです。
特に日本においては、マーケティングの世界で「物質的満足よりも精神的満足」と表現される現代社会において、労働の対価は、「地位・肩書」と「賃金」の時代から「自己成長」や「やりがい」に変化してきています。
従業員に費やしてもらう時間や労力、投下してもらう知識やノウハウなどの「投資」が、従業員に「精神的満足」として、どういうカタチで還元できるかを考えていかないといけない時代でもあるのですから、より積極的に取り組むべきテーマである筈です。
その上で、重ねて取り組んで欲しい課題があります。それは採用段階からのあらゆる人事施策のコンセプトに、従業員の「意欲」と「能力」を、どう高めていくのかを据えていただきたいということです。
現状の従業員のスキルや能力だけが問われるのではなく、今後の成長性への期待も含まれるのが「人的資本経営」の根幹になるからです。
しかし、これは日本的な人材採用、育成では一朝一夕に実現できない課題です。採用段階で「意欲」や「能力」を把握するよりも、挨拶やマナーなど、組織の一員として適切であるかどうかを重視する傾向が強いからです。
「ジョブ型雇用」ではなく「メンバーシップ型雇用」が多いという背景がそうさせてきたのですが、これを「日本的な良さ」と解釈して検討課題を放置するのは無責任と言わざるを得ません。
同一労働同一賃金や改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)という雇用関連法規改正の流れで重視されているのは、従業員の「意欲」と「能力」であるのも明らかです。
厚生労働省が提示しているパワハラ6類型のうち、「過大な要求」や「過小な要求」は、その代表的な例でしょう。
前述のように、東証のコーポレートガバナンスコード改定によって、描いている事業戦略と取締役会メンバーが備えるべきスキルを特定し、各取締役の有するスキルの組み合わせ(スキルマトリックス)を公表することになっています。
これは、ステークホルダーからすると「事業戦略を遂行できそうなスキルや能力を備えているか?」を確認する機会となります。
このトレンドは、自社の戦略に対する人材戦略を描くことになるのですから、自社発信の文脈で語る必要があります。
求職者も応募段階で確認できる情報になりますので、人材獲得競争に大きな影響を与えることも明白です。そう考えれば、株式公開企業のみが取り組むべきテーマとも言えないことも明らかです。
従業員の「意欲」と「能力」の現況を把握してそれをどう高めていくのか、そして業績向上がストーリーとしてどう関係してくるのかを明確化させることが、今後企業に求められる課題となってきます。
人的資本開示が注目されている今こそ、広義での人事戦略と事業戦略の両輪を上手く廻していくために必要なことを、積極的に議論し、言語化すべきときなのではないでしょうか?