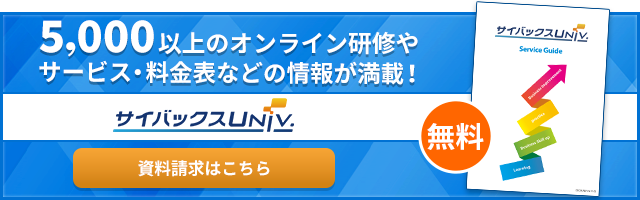最終更新日:2025年06月23日
「部下指導をしないといけないのは重々理解しているが、揚げ足をとられてパワハラで訴えられるのも嫌だし…」とか、「こっちは良かれと思って言っているのに、相手にパワハラって言われたらアウトなんですよね?」とか、ハラスメントという得体の知れない妖怪に恐れおののいて、職場内のコミュニケーションが劇的に減少していると言われています。
この発信者側の加害者意識に関係なく、受信者側の被害者意識で断罪されるかのような恐怖心、本当に必要なのか? それを考えていきたいと思います。
「相手がハラスメントと感じた時点でアウト」は誤解です!
「ハラスメントは、相手がそう感じたら成立してしまうんでしょう?」という話、よく耳にします。しかし、実際にはパワーハラスメントの認定には明確な基準があり、「相手がアウトと言えばアウト」のような主観だけで決まるものではありません。例えば、「労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」第30条の2第1項において、以下のように定義されています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること。」
この条文に照らすと、単に厳しい言葉をかけたからといって即座にパワハラになるわけではありません。重要なのは、
優越的な立場を利用しているか
業務上必要な範囲を逸脱していないか
就業環境に実際に悪影響が生じているか
という客観的な視点です。
加えて、厚生労働省のガイドライン(令和2年告示第5号)では、ハラスメントに該当するかの判断について次のように定められています。
「就業環境が害されるかどうかの判断にあたっては、『平均的な労働者の感じ方』を基準とする」
つまり、「本人が嫌だと感じたかどうか」ではなく、同じような状況で社会一般の労働者が受けた場合に、看過できない程度の支障が生じるかどうかという、客観的な視点が求められるのです。
大事なのは「ハラスメント」と疑われるような言動を起こさないこと
では、なぜ「相手がそう思えばハラスメントになる」という誤解が生まれるのでしょうか?
考えられる理由が2つあります。まず1点目が、ハラスメント的な言動をしている本人に、加害者としての自覚がないことが多いという点があります。現実には、加害認識、自覚が無くても、前述のような基準に該当すれば「ハラスメント」として認定される可能性が高まります。悪気が無くても基準を満たせばアウトになると捉えることが大事でしょう。
もう1点が、ハラスメントの被害を受けた方が、その声を上げる(被害申告をする)ことで、初めてハラスメント事案が表面化するからです。声が上がらない限り誰も認識できませんので、どうしても「声を上げられたらアウト」と感じてしまい、それが行き過ぎてしまって「声さえ上がらなければセーフ」になってしまうケースも多いです。
当然、ハラスメントを「相手によって変わる曖昧なもの」と捉えるのではなく、法的な定義やガイドラインに基づく明確な基準を理解することが重要です。
その基準として、パワハラに関しては厚生労働省が6類型を示しています。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| ①身体的な攻撃 | 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの暴力行為 | 上司が部下の頭を叩く |
| ②精神的な攻撃 | 侮辱、暴言、人格否定など | 「無能」「辞めた方がいい」などの発言 |
| ③人間関係からの切り離し | 意図的に仲間外れにする、隔離する | 一人だけ別室で仕事をさせる |
| ④過大な要求 | 実現不可能な仕事量・期限を課す | 経験のない仕事を丸投げする |
| ⑤過小な要求 | 本来の能力より著しく低い仕事だけを与える | 管理職に掃除だけさせる |
| ⑥個の侵害 | プライベートに過度に立ち入る | 家庭事情・恋愛・病歴をしつこく聞く |
ハラスメントは、単に感情や印象で判断されるものではなく、「優越的関係」「業務の必要性の範囲」「就業環境への影響」など、客観的な要素によって認定されるものです。指導や注意が必要な場面でも、相手の立場を尊重しつつ、適切な言葉選びと接し方を意識することが、ハラスメント防止における第一歩です。しっかりと、現代社会に適した「指導に関するコミュニケーション術」を身につけていきませんか?
コラムの内容をさらに詳しく学べる研修情報
セミナー詳細
| セミナータイトル | ~ハラスメントを疑われたくないから話さない…はモッタイナイ!~ 「●●ハラって言われるかも不安」からの脱却法 |
|---|---|
| 時間 | 約40分 |
| 料金 | 無料 |
| 特別セミナー講師 | 松本 治 氏 (SAP代表/大阪工業大学客員教授/サイバックスUniv.講師) |
| 受講形式 | 2025年6月19日に開催したセミナーの内容を録画したオンデマンド配信です。 |
| 定員 | 1社5名まで |
\★オンデマンド配信視聴のお申込みはこちらから★/
必要事項をご入力の上、お申込みください。(法人企業1社5名まで)
■お問い合わせ
リスクモンスター株式会社 教育サービス課 セミナー事務局
電話番号:03-6214-0351