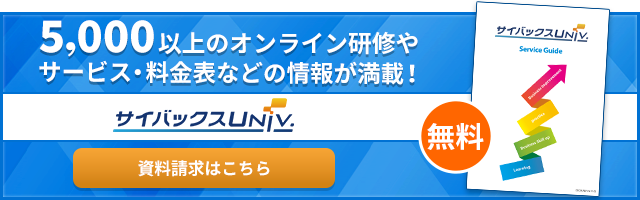皆さんこんにちは。
All for your smilesをモットーに人財育成のお手伝いをさせていただく、リスクモンスターパートナー講師藤島です。
皆さんは「フレームワーク」という言葉を聞いたことがありますか?
「フレームワークを使って考えろ!」
「フレームワークを使って効率的に云々…」
近年では、仕事中の会話や、インターネットの記事を見かけることも珍しくなくなってきました。
そんな、ビジネスの場ではメジャーになってきている「フレームワーク」ですが、そもそもフレームワークが何なのか、一体どういうもので、なぜビジネスの場でメジャーになってきているのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
フレームワークとは
フレームワーク。直訳すると、「枠組み」、「骨組み」、「構造」ですが、ビジネスでよく耳にする「フレームワーク」は、“考え方の枠組みに思考を当てはめる”「ビジネスフレームワーク」のことを指します。
皆さんは仕事をしているときに、様々なことを考えるかと思います。
「自社は業界内においてどのような位置づけにいるのか」
「売り上げを上げていくにはどうしたらいいのか」
「現状自社はどこに注力していくべきなのか」
こういった、仕事上における様々な課題を考える際、まず何から考えればいいかわからなくなり思考が進まない、なんてことはよくあるかと思います。
そういった物事を考えるときに、考えるべきことや考える手順がわかっていると、とても早く仕事を進めることができますよね。
その考えるべきことや考える手順が、考え方の枠組み、ビジネスフレームワークです。
フレームワークのメリットデメリット
ビジネスフレームワークはあらかじめ決められた枠組みによって思考を進めていくため、抜け漏れやダブりがなく、筋道立てて考えることができます。
物事を整理しながら考えることができるので、効率よく、相手にわかりやすく思考を進めていけることがメリットです。
一方で、よくある勘違いに、ビジネスフレームワークを活用すれば課題は解決できると思ってしまう、というのがあります。
ビジネスフレームワークはあくまでも考え方の枠組みに過ぎないので、それ自体で何か答えが必ず出たり、課題解決できたりすることはありません。
また、考える内容によってビジネスフレームワークを使い分けなければ、効率の良さが失われてしまうことがあります。
ビジネスフレームワークはあくまで物事を考えるときの道具でしかないので、使い方が重要になるわけです。
適切な時に適切なフレームワークを
使い方が重要、といいましたが、実はビジネスフレームワークには様々なものがあります。
自社やサービスの状況を把握するのによく使われる3C分析やSWOT分析、消費行動からマーケティング施策を考えるのに使われるAIDEES、組織の全体像を把握し経営方針を考えるのに使われる7S分析…。
マイナスネジにマイナスドライバーがあるのと同様に、考えることに応じて各ビジネスフレームワークがあります。
マイナスネジを締めようとして、プラスドライバーを用いれば、かえってネジを締めにくくなるのと同じで、間違ったビジネスフレームワークを用いると、物事を抜け漏れなく、筋道立てて、効率よく考えていくための道具であるビジネスフレームワークが、かえって非効率で邪魔なものとなってしまいます。
ビジネスフレームワークを機能させるためには、適切なビジネスフレームワークを選択しなければなりません。
サイバックスUnivでは、道具であるビジネスフレームワークを紹介しつつ、どういう場面で使うのが有効なのかという使い方を学んでいく講座を用意しています。
物事を効率よく考えたい、ビジネスフレームワークという道具の使い方を知りたい。
そんな形でビジネスフレームワークに興味をお持ちの方は、ぜひ、フレームワークの研修を受講してみてください。