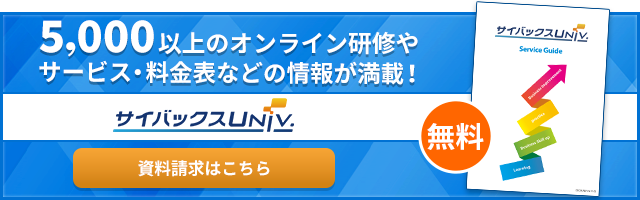皆さんは仕事をしている中で、部下を叱ることが多いでしょうか?ほめることが多いでしょうか?
仕事をしていくうえで大事なことは結果を出すことです。
そのため、部下の不適切な行動について注意や指導をするケースは少なくないでしょう。
その中で、なかなか部下が成長せず叱ることが多くなる、というのはよくあることです。
一方で、最近はハラスメントやコンプライアンスについても厳しく言われるようになり、叱るということを躊躇してしまったり、ほめて伸ばすようにという風潮を強く感じてしまい、どのようにして部下を叱ればいいのか、またはほめればいいのか悩んでいるという声を多く耳にします。
今回は、効果的なほめ方、叱り方を学べる「部下の成長を促す ほめる・叱るコミュニケーション術」の紹介をいたします。
1.部下の成長を促せる人は「叱る目的」と「ほめる目的」を知っている
・いつも部下を叱ってしまう
・本当は叱りたいけど躊躇してしまう
・ほめるのが苦手
・ほめようとして下手に出すぎてしまう
上記のように部下を叱ること、ほめることがうまくできない人の多くは、漫然と部下を叱ったり、ほめたりしています。
皆さんはどんな時に部下を叱っていますか?どんな時に部下をほめていますか?
何のために叱っていますか?ほめていますか?
部下の成長を促すような叱り方、ほめ方ができている人は、叱ること、ほめることの目的を知っています。
2.叱る目的
叱ることの目的は2つあります。
①社会的常識や基準から逸脱した行動を戒めるため
②業務上のミスやあるべき水準に達していないことを部下に自覚させるため
気をつけないといけないのは、叱るという行動に先立ち、「きちんと教える」という行動が必要ということです。
教えていない・教え方が悪いという状態で①、②に該当するからと叱られた部下は、理不尽に感じて嫌になってしまいます。
上記に気をつけつつ、目的をもって叱ることを心がけましょう。
部下を叱る場面というのは、人材育成のチャンスなのです。
3. ほめる目的
ほめることの目的は、「良い行動を習慣化させること」です。
気をつけないといけないことは、結果だけでなく「プロセスや行動もほめる」ということ。
そのために、部下のことをよく観察しておく必要があるということです。
部下をほめる際、多くの人は良い結果が出たときにほめがちです。
良い結果というのは、幸運が重なってたまたま出るというものもあり、必ずしも良い行動の結果についてくるものだけではありません。
そのため結果だけほめても再現性を得られず、部下が育たないことがあります。
上記を意識して、目的をもってほめるために日頃から部下のことをよく観察することを心がけましょう。
4. まとめ
普段から部下育成や、人材育成がきちんと行われていれば、叱るケースは減り、ほめる機会が多くなるはずです。
部下が成長していないため叱る機会が多いというのは、実は「部下育成をしていない」ということになるかもしれません。
叱る目的、ほめる目的を理解し、部下の成長を促すコミュニケーションが大切になります。
「そうはいっても、部下をほめるのは苦手だ…。」
「本当は適切に部下を叱りたいけどどうしても躊躇してしまう…。」
上記のように悩まれている方も、叱る目的・ほめる目的の理解に加えて、叱り方・ほめ方のポイントを押さえて使い分けることで、部下の成長を促すコミュニケーションが取れるようになります。
「部下の成長を促す ほめる・叱るコミュニケーション術」の研修で、効果的なほめ方、叱り方を学び、部下の成長を促すことで業務効率や精度を一緒に上げていきましょう。
コラムの内容を学べる公開研修情報
- 部下の成長を促すほめる・叱るコミュニケーション術
日程:2023年2月16日(木曜日)15:00~17:00
詳細はこちら
【サイバックスUniv.事務局からご案内】
- 【無料!お役立ち資料】企業が行うべきハラスメント対策とは?
ハラスメントが企業や人に与える影響や、予防策について解説いたします。
【お役立ち資料の内容】
1.ハラスメントに対する認識
2.急増しているハラスメントの種類
3.ハラスメントが与える影響
4.ハラスメント撲滅の具体的な取り組み
5.当社サービス活用事例